静岡新聞のコラム「窓辺」

文/小林不二也(重症児者通所施設でらーと)
第十回
もっとも弱いものをもれなく守る
もっとも弱いものをもれなく守る
この言葉は、重症児(者)を守る会三原則の一つです。日本の重症児(者)福祉の歴史は守る会が切り開いたといっても過言ではない。静岡県の重症児(者)を守る会が4日、結成50周年記念の集いを開催する。50年前、重症児(者)の福祉はとても貧困で、何も無いといっても過言ではなかったのです。この50年間の親たちの取り組みが当時の行政を動かして、今があるのです。
福祉制度の変遷を学ぶとはっきりわかることがあります。様々な制度やサービスが生まれてきていますが、それらが生まれるまでには、当事者の訴えや運動が先にあったということです。つまり福祉の対象者がしっかりと社会に現状を知らしめたことで、制度化されてきているということです。最初から配慮されているものは無いということです。この50年は日本の民主化が大きく進んだと同時に弱い立場の人にも光が当てられてきた50年でした。「もっとも弱いものをもれなく守る」この原則が民主主義の魂のように感じます。
たった50年です。今新たに福祉の職場に就き、日々思い悩んでいる仲間にぜひ伝えたいこととして、このたった50年間で大きく進んだ重症児(者)福祉の歴史は、50年前に苦悩を重ねたごく少数の親たちからスタートしている。今の苦悩は必ず明日の福祉につながっていくことを。
福祉制度の変遷を学ぶとはっきりわかることがあります。様々な制度やサービスが生まれてきていますが、それらが生まれるまでには、当事者の訴えや運動が先にあったということです。つまり福祉の対象者がしっかりと社会に現状を知らしめたことで、制度化されてきているということです。最初から配慮されているものは無いということです。この50年は日本の民主化が大きく進んだと同時に弱い立場の人にも光が当てられてきた50年でした。「もっとも弱いものをもれなく守る」この原則が民主主義の魂のように感じます。
たった50年です。今新たに福祉の職場に就き、日々思い悩んでいる仲間にぜひ伝えたいこととして、このたった50年間で大きく進んだ重症児(者)福祉の歴史は、50年前に苦悩を重ねたごく少数の親たちからスタートしている。今の苦悩は必ず明日の福祉につながっていくことを。

第九回
いのち
いのち
私は先日、とても大切な人を二人亡くした。一人は私の実兄58歳、末期がんでした。もう一人は私が在宅重症心身障害児(者)の支援のきっかけを作ってくれた、重度の障害を持つ、R君22歳でした。まだ二人を亡くした実感はわきませんが、体の中をスーっと冷たい風が通り過ぎたような感覚を覚えたと同時に力が失せていく何とも寂しい気持ちになりました。兄の母親は健在、22歳のR君の両親ももちろん健在です。昔から言われている「逆さを見る」という悲しい形となりました。どちらの葬儀もとても多くの人が最後のお別れをしてくれました。病気や障害と闘いながら最後の最後まで精一杯生きた二人が、平均余命まで生きられたら、どれくらい多くの人と関わり、どれくらい多くの人に影響を与えたかを考えると「生きること」「いのち」の大切さをつくづく感じる。
統計によると年間3万人近くの人が自ら命を絶っている。さまざまな事情があるのだろうが、一人で生きている人は誰一人居ない。多くの人とのかかわりの中で皆、もがきながら生きている。超重症児と呼ばれる濃厚な医療を必要とする児と関わると、このいのちの重さを痛感する。1日1日がいかに大切かを教えられる。自分が悩んでいることがとても、ちっぽけなことに思えてくる。二人の分までしっかり生きなきゃと強く感じさせてくれる。
統計によると年間3万人近くの人が自ら命を絶っている。さまざまな事情があるのだろうが、一人で生きている人は誰一人居ない。多くの人とのかかわりの中で皆、もがきながら生きている。超重症児と呼ばれる濃厚な医療を必要とする児と関わると、このいのちの重さを痛感する。1日1日がいかに大切かを教えられる。自分が悩んでいることがとても、ちっぽけなことに思えてくる。二人の分までしっかり生きなきゃと強く感じさせてくれる。
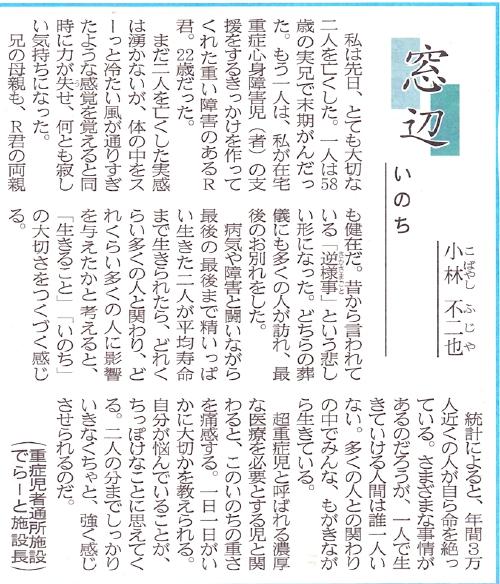
第八回
「ぞうさんだより」に想う
「ぞうさんだより」に想う
在宅医療ケアのある子をもつ親の会「ぞうさんの会」から会員に送られるたよりが届きました。この便りを読んでいて改めて、気づいたことを記す。この会の会長さんが会員の様子や声をまとめた内容が中心となっているが、新たに3名の新会員が写真入で紹介されていた。紹介はそのお母さんが自らの家族の様子を書いたものであるが、写真や記載している様子からもみな最重度でまだ学齢前なのに、何度も死のふちを乗り越えてきたことが容易に想像できる状態のお子さんでした。
いずれのお母さんの文章からも共通に感じられたことが、生きることへの謙虚さと周囲への感謝とお子さんへの限りない愛情でした。これらの姿勢はどこから来るのだろう?間違いなく、生後まもなくから重い病気や障害と闘いながら「明日もう1日、元気でいてほしい」「明日は今日よりもよくなってほしい」と願い続けて、支えた活動からだと感じる。その親子の願いを身近で接する医療職・福祉職・友人・親戚がその姿勢に心打たれて、つながっていく。この力の源は、重い障害をもつ本人が呼び起こしていることに気づかされる。私の施設の親さんたちの力強さにも、いつも驚かされているが、「やっぱり共通なんだ」と知らされた。この力が日本中に広がればすごいことになると想うのは私だけでしょうか。
いずれのお母さんの文章からも共通に感じられたことが、生きることへの謙虚さと周囲への感謝とお子さんへの限りない愛情でした。これらの姿勢はどこから来るのだろう?間違いなく、生後まもなくから重い病気や障害と闘いながら「明日もう1日、元気でいてほしい」「明日は今日よりもよくなってほしい」と願い続けて、支えた活動からだと感じる。その親子の願いを身近で接する医療職・福祉職・友人・親戚がその姿勢に心打たれて、つながっていく。この力の源は、重い障害をもつ本人が呼び起こしていることに気づかされる。私の施設の親さんたちの力強さにも、いつも驚かされているが、「やっぱり共通なんだ」と知らされた。この力が日本中に広がればすごいことになると想うのは私だけでしょうか。
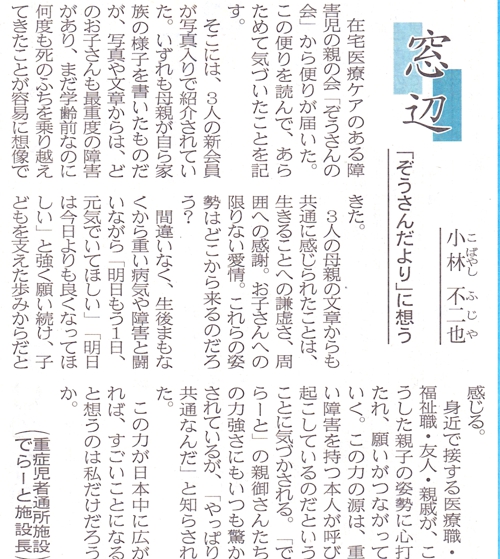
第七回
インクルーシブ教育
インクルーシブ教育
「障害の有無に関わらず誰もが地域の学校で学べる教育」という意味だが、私はこの言葉を「線引きをしない教育」と理解している。
重度の障害を持つ我が子を、地域の学校に入学させたいと頑張っている保護者がいるが、なかなか実現しない。理由は、その子にあった授業ができないとか、設備が不十分とか、いろいろ言われているが、結局は今の通常の学校教育では彼らを受け入れる理念が不足しているのだと思う。
想像してみてほしい。通常の学級に寝たきりの重症児がいるとする。「難しいだろう」という声が聞こえてきそうだが、私はとても良いと思う。
例えば、先生が生徒に集まるよう指示を出せば、数秒間で整列するのが今の現場だろう。ここに寝たきりの重症児がいたら?その子は指示に従い、自力で移動することはできない。この時、クラスメートはどのように動くだろうか?
この指示一つとっただけでも、いろいろな学びの場面が想像できる。学校が、社会に出て生き抜いていくための学習をする場所だとしたら、いろいろな人がいて当然だし、多様な人から学ぶことこそ大切だと思う。
学力や能力で線を引いて「できる児」を育てるだけが教育ではないはずだ。人は一人一人みんな違うもの。クラスに重症児がいたら、そんな当たり前のことが日常的に感じられる。こんな経験をした子どもが社会に羽ばたけば、少しずつ社会が変わっていけそうな気がする。
重度の障害を持つ我が子を、地域の学校に入学させたいと頑張っている保護者がいるが、なかなか実現しない。理由は、その子にあった授業ができないとか、設備が不十分とか、いろいろ言われているが、結局は今の通常の学校教育では彼らを受け入れる理念が不足しているのだと思う。
想像してみてほしい。通常の学級に寝たきりの重症児がいるとする。「難しいだろう」という声が聞こえてきそうだが、私はとても良いと思う。
例えば、先生が生徒に集まるよう指示を出せば、数秒間で整列するのが今の現場だろう。ここに寝たきりの重症児がいたら?その子は指示に従い、自力で移動することはできない。この時、クラスメートはどのように動くだろうか?
この指示一つとっただけでも、いろいろな学びの場面が想像できる。学校が、社会に出て生き抜いていくための学習をする場所だとしたら、いろいろな人がいて当然だし、多様な人から学ぶことこそ大切だと思う。
学力や能力で線を引いて「できる児」を育てるだけが教育ではないはずだ。人は一人一人みんな違うもの。クラスに重症児がいたら、そんな当たり前のことが日常的に感じられる。こんな経験をした子どもが社会に羽ばたけば、少しずつ社会が変わっていけそうな気がする。

第六回
障害者への理解
障害者への理解
障害者施設の多くは、人里はなれた山の中にあります。障害者は山の中でひっそり暮らしていたほうが幸せだと考えられていたと思われます。厚生労働省はここ数年「施設から地域へ」と施策を大きく転換しています。具体的には、これまでの大規模な入所施設ではなく、グループホームなど数名の共同生活を住宅地に求めることを推し進めていますが、地域の反対と無理解でなかなか進んでいないのが現状です。障害者が共同生活をするグループホームを作るとき、地域の住民に説明会を行い、理解を求めることになっています。これは変な話ですよね。たとえば、大学生がルームシェアで何人かで共同生活するのに、地域住民に理解を求めるための説明会をするでしょうか?
障害者は健常者に比べて圧倒的な少数派です。身内に障害者がいない人は、障害者を身近に感じる機会はまず無いでしょう。知らないことに対する抵抗感が働いているのだと思われます。私は反対する住民を批判する前に、私たち(本人・家族・関係者)がもっと自然に社会に知ってもらう努力をしなければいけないと感じています。ハンディキャップを持ちながら、懸命に生きる彼らに常に接して、彼らの魅力を感じている私たちがしっかりと語り、障害のことを知らない多くの人との通訳者のような役割を果たしていくことで、共生社会は実現すると確信しています。でら~とのある広見地区の皆さんのように。
障害者は健常者に比べて圧倒的な少数派です。身内に障害者がいない人は、障害者を身近に感じる機会はまず無いでしょう。知らないことに対する抵抗感が働いているのだと思われます。私は反対する住民を批判する前に、私たち(本人・家族・関係者)がもっと自然に社会に知ってもらう努力をしなければいけないと感じています。ハンディキャップを持ちながら、懸命に生きる彼らに常に接して、彼らの魅力を感じている私たちがしっかりと語り、障害のことを知らない多くの人との通訳者のような役割を果たしていくことで、共生社会は実現すると確信しています。でら~とのある広見地区の皆さんのように。

第五回
福祉の仕事の社会的評価
福祉の仕事の社会的評価
福祉の仕事について10人中10人が「大変な仕事だ」と評価する。それなのに、福祉の仕事に携わる職員の賃金は全体的にとても低い。なぜだろう?
人間が生きていくことを直接支える仕事。人生を支えると言っても過言でないほど大切な役割を果たしているのに、他の仕事よりも賃金が低い理由は何か。
理由の一つは、人助けは金銭の見返りを求めずに善意で行うもので、金銭による評価はむしろその善意を踏みにじることにつながるという誤解だ。
二つ目は、膨れあがる社会保障費の問題。福祉従事者の賃金の出どころとなる社会保障給付費は、少子高齢化で増加の一途をたどっている。この主な財源は国民の血税。福祉従事者の賃金上昇のために社会保障費を増やすことは増税につながるため、反発する人も少なくないはずだ。
いずれにせよ突き詰めて考えれば、福祉の仕事の賃金は、この仕事の専門性を社会がいかに評価しているかの反映だと思う。善意で行う人助けと、専門職としての福祉の位置づけが、社会で混同されているために職業としての福祉がきちんと評価されず、現場の待遇はなかなか改善されないのではないか。
物が豊かになることは素晴らしいことだが、社会的弱者を含む全ての人の幸せも大切なことだ。ものづくりと同様、福祉の仕事も正当に評価されるべきなのに、社会ではこの認識がいまひとつのように感じられる。
この価値観を変えられる日は来るのだろうか・・・。
人間が生きていくことを直接支える仕事。人生を支えると言っても過言でないほど大切な役割を果たしているのに、他の仕事よりも賃金が低い理由は何か。
理由の一つは、人助けは金銭の見返りを求めずに善意で行うもので、金銭による評価はむしろその善意を踏みにじることにつながるという誤解だ。
二つ目は、膨れあがる社会保障費の問題。福祉従事者の賃金の出どころとなる社会保障給付費は、少子高齢化で増加の一途をたどっている。この主な財源は国民の血税。福祉従事者の賃金上昇のために社会保障費を増やすことは増税につながるため、反発する人も少なくないはずだ。
いずれにせよ突き詰めて考えれば、福祉の仕事の賃金は、この仕事の専門性を社会がいかに評価しているかの反映だと思う。善意で行う人助けと、専門職としての福祉の位置づけが、社会で混同されているために職業としての福祉がきちんと評価されず、現場の待遇はなかなか改善されないのではないか。
物が豊かになることは素晴らしいことだが、社会的弱者を含む全ての人の幸せも大切なことだ。ものづくりと同様、福祉の仕事も正当に評価されるべきなのに、社会ではこの認識がいまひとつのように感じられる。
この価値観を変えられる日は来るのだろうか・・・。

第四回
「親亡き後」という言葉
「親亡き後」という言葉
この言葉は、障害福祉の現場でよく耳にする。障害と無関係な家族で使われることはまれだろう。これは、障害児を産んだらその親が死ぬまで責任を持つことが前提という意味の込められた言葉だ。「自立」とは真逆の言葉と言っても過言でない。
日本の障害福祉の歴史は差別と偏見との戦いだった。若い人は聞いたこともないかもしれないが、「座敷牢」という表現がある。障害児を家の一室に隠し、近隣に存在を気づかれないよう生活させていたことを表していて、まさに悲惨な歴史の象徴だ。
「親亡き後」を心配する障害者の親はいまだに多い。だからこの言葉が多用されるのだが、私たちはこの言葉を使うことを恥ずかしいと思わなければいけない。
特別支援学校が義務化され、学校教育で社会に巣立つ力を養っている。どんなに重い障害者でも、親の人生とは別の人生を描ける社会にしなければならいない。私たち福祉関係者はそれを社会に訴える立場。それなのに、この言葉を使っているのはとても悲しいことだ。
この言葉は、日本の障害者福祉がまだまだだと裏付けてしまっている。どんなに重い障害があっても、普通に生きていける社会が実現すれば、この言葉は死語となるはずだ。その日が訪れることが、本当に豊かな社会の実現の第一歩なのではないだろうか。
日本の障害福祉の歴史は差別と偏見との戦いだった。若い人は聞いたこともないかもしれないが、「座敷牢」という表現がある。障害児を家の一室に隠し、近隣に存在を気づかれないよう生活させていたことを表していて、まさに悲惨な歴史の象徴だ。
「親亡き後」を心配する障害者の親はいまだに多い。だからこの言葉が多用されるのだが、私たちはこの言葉を使うことを恥ずかしいと思わなければいけない。
特別支援学校が義務化され、学校教育で社会に巣立つ力を養っている。どんなに重い障害者でも、親の人生とは別の人生を描ける社会にしなければならいない。私たち福祉関係者はそれを社会に訴える立場。それなのに、この言葉を使っているのはとても悲しいことだ。
この言葉は、日本の障害者福祉がまだまだだと裏付けてしまっている。どんなに重い障害があっても、普通に生きていける社会が実現すれば、この言葉は死語となるはずだ。その日が訪れることが、本当に豊かな社会の実現の第一歩なのではないだろうか。

第三回
「入所式に思う」
「入所式に思う」
重症児者通所施設「らぽ~と」では今春、新たに3人の利用者さんを迎えました。うち1人は15年前に国立病院で開いた療育相談訓練会(在宅親子の憩いの場)に参加していたY君でした。彼の母親が当時話していたことが今でも心に残っています。
それは産後に主治医から言われた一言。「脳に重い障害があり、ほぼ植物状態。命も危ういかもしれない」。それを聞いた母親は病院からの帰り道、運転中に涙で前が見えなくなり、車を脇に寄せて号泣したそうです。
私がY君親子と出会ったのは、その言葉から数年後のことでした。確かに彼の障害の状態は重く、寝たきりではありましたが、呼びかけに対する反応もあり、植物状態とはかけ離れていました。なぜ医師は出産後に絶望を伝えたのでしょうか?
重い病気について、医師が最悪の場合を想定して説明することはよくあることです。訴訟時代といわれる現代、その傾向はますます強くなっているかもしれません。
ただ、親は医師の言葉から、たとえわずかでも希望を見出して生きたいのだと思います。丁寧な説明と寄り添いで、絶望だけを伝えることは避けられると思います。
このエピソードは人を支援する仕事にとって、とても貴重な教訓です。入所式で、母親から職員に当時の話をしてもらいました。入所したY君は現在18歳。元気に歌を口ずさみながら自力で車いすを押し、施設内を走り回っています。彼の今後に夢を感じます。
それは産後に主治医から言われた一言。「脳に重い障害があり、ほぼ植物状態。命も危ういかもしれない」。それを聞いた母親は病院からの帰り道、運転中に涙で前が見えなくなり、車を脇に寄せて号泣したそうです。
私がY君親子と出会ったのは、その言葉から数年後のことでした。確かに彼の障害の状態は重く、寝たきりではありましたが、呼びかけに対する反応もあり、植物状態とはかけ離れていました。なぜ医師は出産後に絶望を伝えたのでしょうか?
重い病気について、医師が最悪の場合を想定して説明することはよくあることです。訴訟時代といわれる現代、その傾向はますます強くなっているかもしれません。
ただ、親は医師の言葉から、たとえわずかでも希望を見出して生きたいのだと思います。丁寧な説明と寄り添いで、絶望だけを伝えることは避けられると思います。
このエピソードは人を支援する仕事にとって、とても貴重な教訓です。入所式で、母親から職員に当時の話をしてもらいました。入所したY君は現在18歳。元気に歌を口ずさみながら自力で車いすを押し、施設内を走り回っています。彼の今後に夢を感じます。

第二回
「K君から教えられたこと」
「K君から教えられたこと」
今から20年以上前の話である。国立病院の重症児(者)病棟にK君は入所していた。K君は重度の脳性まひである。K君の状態は寝たきりで、不随意運動と言って、手足がいつもバタバタと勝手に動いてしまう。知的な遅れはあったが、日常会話は可能だった。しかし、その言葉は明瞭性にかけて、なかなか聞き取れなかった。でも彼は職員と会話をするのが大好きで、忙しく走り回る職員を呼び止めては、話しかけるのが日常であった。
彼の言葉は難解で1回聞いただけでは、わからないことがほとんどであった。だから職員は彼の会話に付き合うと、一人で聞き取れず、周りの職員を呼んで彼の周りに数名の職員が、囲みこんで彼の発する難解な一言を聞き取るのに、数十分かかることもしばしばであった。彼はわかってくれるまで、手足をバタバタとさせながら、汗びっしょりになって、たった一言を懸命に職員に聞き取ってもらえるまで伝える。彼の体を気遣って、「もういいよ」と言って聞き取れないまま去ってしまう職員もいる。もちろん彼は不満である。体がつらいのは彼である。つらくてもその一言を聞いてもらいたいのである。
私たちはこんなに一生懸命に誰かに一言を伝えるために努力しているだろうか?K君のこの努力の尊さに不自由でない私たちは、学ばなければいけない。「僕はわかってもらうまで何度でも言うよ!」の姿勢に。
彼の言葉は難解で1回聞いただけでは、わからないことがほとんどであった。だから職員は彼の会話に付き合うと、一人で聞き取れず、周りの職員を呼んで彼の周りに数名の職員が、囲みこんで彼の発する難解な一言を聞き取るのに、数十分かかることもしばしばであった。彼はわかってくれるまで、手足をバタバタとさせながら、汗びっしょりになって、たった一言を懸命に職員に聞き取ってもらえるまで伝える。彼の体を気遣って、「もういいよ」と言って聞き取れないまま去ってしまう職員もいる。もちろん彼は不満である。体がつらいのは彼である。つらくてもその一言を聞いてもらいたいのである。
私たちはこんなに一生懸命に誰かに一言を伝えるために努力しているだろうか?K君のこの努力の尊さに不自由でない私たちは、学ばなければいけない。「僕はわかってもらうまで何度でも言うよ!」の姿勢に。
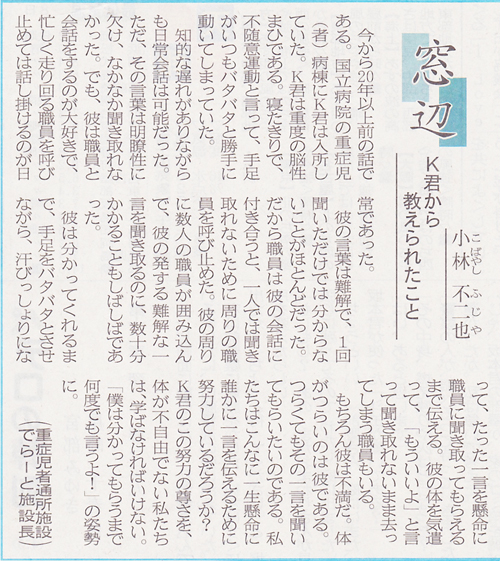
第一回
「重症心身障害児(者)について」
「重症心身障害児(者)について」
私の仕事は、重症心身障害児(者)以下重症児(者)とその家族の支援をすることです。重症児(者)とは、重度の身体障害と重度の知的障害を併せ持つということです。その多くが寝たきりで、すべてに介助を必要とする方々です。児(者)と併記しているのは、この名称が決められた50年前に、これほど障害の重い状態では、ほとんどが成人を迎えられないだろうと当時の厚生省は考えたと聞いています。だから児中心で(者)としたのです。重症児(者)の福祉は、その障害の重さのために、病院の中の入所施設でしか行えませんでした。50年の時を経た今、命を守るということで大きな成果を挙げました。
一方、多くの入所施設は大人が多数を占め、新たな児を受け入れられない状態になっています。かと言って、現在在宅で暮らしている重症児(者)親子の多くは、病院への入所を希望しているわけではありません。入所している方たちよりも重い医療行為を日々、在宅で行いながらも、自分の生まれ育った地域で生活することを望んでいます。この親子の大切な日々を支えるためには、進んだ新生児医療だけではなく、病児を抱えて生きている親子が豊かな生活を送るための「支える医療」が不可欠なのです。
成熟した社会となるには、このような、必死に生きる在宅重症児(者)親子を支えなければいけません。私たち一人一人が、協力していくことで実現できると思います。
一方、多くの入所施設は大人が多数を占め、新たな児を受け入れられない状態になっています。かと言って、現在在宅で暮らしている重症児(者)親子の多くは、病院への入所を希望しているわけではありません。入所している方たちよりも重い医療行為を日々、在宅で行いながらも、自分の生まれ育った地域で生活することを望んでいます。この親子の大切な日々を支えるためには、進んだ新生児医療だけではなく、病児を抱えて生きている親子が豊かな生活を送るための「支える医療」が不可欠なのです。
成熟した社会となるには、このような、必死に生きる在宅重症児(者)親子を支えなければいけません。私たち一人一人が、協力していくことで実現できると思います。








